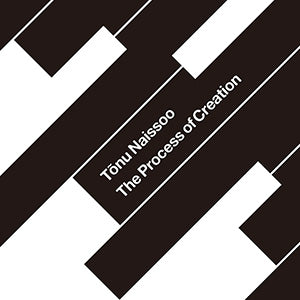
THE PROCESS OF CREATION
Share

~トヌー・ナイソー、あるいは熟練のピアニストに潜む「荒ぶる魂」~
欧州、それも北欧、東欧といった、欧州なりの「辺境」から無名のアーティストを一本釣りしてきて紹介する、というのがアトリエ・サワノのお家芸だった。
どんなことにでも毀誉褒貶はつきものだから、サワノの仕事に諸手を挙げての称賛ばかりでないことは分かっているが、この切り口だけは、日本に幾多ジャズレーベルが存在しようと他にはなかったものだ。そこは間違いない。
ウラジミール・シャフラノフも、サワノの紹介(敢えて「発見」と呼んでもバチは当たらない気がするが)がなければ "WHITE NIGHTS"という作品のレアリティだけを徒花として、メインのシーンとは無縁だった、かも知れない。ヨス・ヴァン・ビーストも、ロバート・ラカトシュも。
バルト三国のひとつであるエストニアにもジャズ・シーンがあるのだ、ということすら、もしかしたら我々は知らずにいた可能性だってある。
もちろん、旧ソヴィエトの強い影響下にあった北方の小国にもジャズはあり、しかも端倪すべからざるピアニストがいるのだ、ということをサワノは教えてくれた。
名を、Tõnu Naissoo、トヌー・ナイソーという。

本邦初登場は2005年にまで遡る。アルバムは WITH A SONG IN MY HEART (AS046) 。いかにもサワノらしく、スタンダード・ナンバーを並べた趣味の良い内容で、広く支持されることになり、その成功を出発点としてコンスタントに新作を発表して行く。そして、デヴュー・アルバムこそ全面的にサワノの色合いだったが、続くYOU STEPPED OUT OF A DREAM (AS061) からは徐々にアーティストとしての「我」が現れて来た(一作目が上手く行けば、その次ではアーティストの希望が入ってくることは、インセンティブという意味でも当然だろう)。それは、一般的にジャズ・スタンダードとして知られるもの以外の、言わば、「トヌー・ナイソーにとってのスタンダード」が数曲チョイスされる、という形をとり、ボブ・ディランの "Lay lady Lay" やジミ・ヘンドリックス(ん?…ジミヘン?)の "Angel" が演奏されている。


このあたりから、当時すでに50代後半の年齢だったピアニストの音楽的なルーツが、所謂ジャズ以外の部分に(も)あるようだ、ということに我々は気づくことになった。
一言にするなら、それはRock、である。
ジャズ・ロックというと誰でもリー・モーガンの "Sidewinder" あたりを思い浮かべる。それはロック・ビートの文脈でジャズを演奏する、というものだった。ビートこそそれまでとは違うが、中身はハード・バップだ。
それでは、正味のロック(やポップ、フォーク)ナンバーを素材、つまり、ガーシュインやコール・ポーター曲と同列に扱ったのはいつ頃からになるのか?
個人的に、それはキース・ジャレットがまんま The Byrds のアレンジを用いたディランの "My Back Pages" を演奏した時からではないのだろうか?と考えている。
ジャズの世界に、ロック・ナンバーがスタンダードとしての「市民権」を得て行くのは、このあたりからだろう。
そして、想像するに、トヌー・ナイソーはそれに直撃されたのではあるまいか? 彼がそのタイトルも MY BACK PAGES (AS113) というアルバムで、先達にオマージュを捧げているのはご存知の通りだが、それでなくとも、彼のタッチの中にキースの影を見出すことは容易いことだった。

…そうか、トヌーさん(レーベルとの付き合いが、気が付くと15年以上に及んでいるせいもあり、自然とそう呼んでしまう)のアイドルはキース・ジャレットで、やりたいことはロックのジャズ・アダプテーションなのだな、ということが分かってくる。
その結果生まれたものが、「三部作」…FIRE (AS128) 、R (AS148) 、 1967 (AS159) という3枚のアルバムだった。



ここで「トヌー節」は選曲、演奏の面で全開となる。
特に "R" が凄い。
ビートルズ、ストーンズは序の口で、ニルヴァーナはやるわ、オアシスはやるわ、コールドプレイ("Viva la Vida"、いやー、シブい!)に、あげくガンズ&ローゼスと来る。
いかにも好々爺然として実年齢よりも穏やかに見えるトヌーさんの本音はここにあったのか。ところが、これがまたカッコいいんだわ。こんなピアノ・トリオ・アルバムは他にないので、未聴の方はお試しになれば、と思う。
1967 は、そのトヌーさんのルーツに最もよりそった企画であり、私自身選曲にも参加しているので、思い入れも一入だが、実は "R" に較べれば穏当なくらいだ。
考えてみれば、1951年生まれのトヌーさんは、東側の陰鬱な空気の下で、青春のただ中、西側世界への憧憬を、音楽を通じて育み続けていたのかも知れない。
その結果がロックに向かったとしてもそれは自然なことだし、それを自在にジャズへと消化(昇華でもある)したキースを範とすることになったのもまた必然だったのだろう。
さて、そのトヌーさんから届いた新しい仕事は、そうしたトヌーさんの「素」が鮮やかに表現されたものとなっている。
なんと、ソロ・パフォーマンス。
しかも、全曲が自作のマテリアルだ。
トヌーさんのソロと言えば、以前にも ALONE (AS088) があるが、そちらはポップ、ロックを含むとは言え、基本的にスタンダード集だったから、今度はまるで色合いが違う。

ばかりではない。
自作曲とは言いながら、そこには明確なテーマ・メロディが示されていない。
おそらくは、ピアノに向かい、インプロヴィゼーションとして展開したものだけがここに集められているのだ。ジャズ・ピアノの世界でそんなことをやって来た人は、トヌーさんのアイコンであるはずのキース・ジャレットを措いて他には幾人もいない。
だとすると、それはスケッチ、習作のようなものなのか?
決して、そうなのではない。
それぞれのナンバーに付されたタイトルの世界観と向き合って作り上げられただろう即興演奏は、いつものトヌーさんでありながら、どこか抜き差しならない緊張感を孕み、独特の美意識に彩られている。紛れもない「作品」がそこに現出しているのだ。
つまり、これは THE PROCESS OF CREATION というタイトルが示す通り、トヌー・ナイソーというピアニストが自らの音楽世界を作り上げていく道のりの記録であると同時に、そういう形でしか語り得ない、そう、魂の形の表現なのである。
この誠実さ、いかにもトヌーさんらしいではないか。
御年70歳、誰しもが円熟を意識する人生のステージにあって、美音を連ねた演奏を結果として生み出しながら、その原動力となっているのは、創作に向かって己を突き動かす「荒ぶる魂」であるに違いないのだから。

だから、こう言ってみるのも良いかも知れない。
これは優れたジャズ・ピアニストによるパフォーマンスだが、その実体はRock に外ならない、と。
そして、それは確実に、あなたを勇気づける音楽なのだ。
北見 柊
------------------------------------------------------------
The Process Of Creation
Produced by Tõnu Naissoo
All compositions by Tõnu Naissoo
Tõnu Naissoo : Steinway D concert grand piano
Recorded August 13 & 14 at Tubin Hall, Heino Eller Music School, Tartu, Estonia
Recorded, mixed and mastered by Martin Hein
Piano technician: Veli Sarv
Photos: Tõnu Naissoo / Martin Hein
Special Thanks to Heino Eller Tartu Music School
------------------------------------------------------------
トヌーナイソー作品を定額ストリーミングサービスで聴く
Spotify / Apple Music / Amazon Music / YouTube Music
※音楽配信サービスの利用する場合は各サービスにご登録・ご契約ください。
